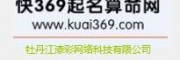そのころ、東京中の町という町、家という家では、ふたり以上の人が顔をあわせさえすれば、まるでお天気のあいさつでもするように、怪人「二十面相」のうわさをしていました。
「二十面相」というのは、毎日毎日、新聞記事をにぎわしている、ふしぎな 盗賊とうぞくのあだ名です。その賊は二十のまったくちがった顔を持っているといわれていました。つまり、変装へんそうがとびきりじょうずなのです。
どんなに明るい場所で、どんなに近よってながめても、少しも変装とはわからない、まるでちがった人に見えるのだそうです。老人にも若者にも、 富豪ふごうにも乞食こじきにも、学者にも無頼漢ぶらいかんにも、いや、女にさえも、まったくその人になりきってしまうことができるといいます。
では、その賊のほんとうの年はいくつで、どんな顔をしているのかというと、それは、だれひとり見たことがありません。二十種もの顔を持っているけれど、そのうちの、どれがほんとうの顔なのだか、だれも知らない。いや、賊自身でも、ほんとうの顔をわすれてしまっているのかもしれません。それほど、たえずちがった顔、ちがった姿で、人の前にあらわれるのです。
そういう変装の天才みたいな賊だものですから、警察でもこまってしまいました。いったい、どの顔を目あてに捜索したらいいのか、まるで見当がつかないからです。
ただ、せめてものしあわせは、この盗賊は、宝石だとか、美術品だとか、美しくてめずらしくて、ひじょうに高価な品物をぬすむばかりで、現金にはあまり興味を持たないようですし、それに、人を傷つけたり殺したりする、ざんこくなふるまいは、一度もしたことがありません。血がきらいなのです。
しかし、いくら血がきらいだからといって、悪いことをするやつのことですから、自分の身があぶないとなれば、それをのがれるためには、何をするかわかったものではありません。東京中の人が「二十面相」のうわさばかりしているというのも、じつは、こわくてしかたがないからです。
ことに、日本にいくつという貴重な品物を持っている富豪などは、ふるえあがってこわがっていました。今までのようすで見ますと、いくら警察へたのんでも、ふせぎようのない、おそろしい賊なのですから。
この「二十面相」には、一つのみょうなくせがありました。何かこれという貴重な品物をねらいますと、かならず前もって、いついく日にはそれをちょうだいに参上するという、予告状を送ることです。賊ながらも、不公平なたたかいはしたくないと心がけているのかもしれません。それともまた、いくら用心しても、ちゃんと取ってみせるぞ、おれの腕まえは、こんなものだと、ほこりたいのかもしれません。いずれにしても、 大胆不敵だいたんふてき、傍若無人ぼうじゃくぶじんの怪盗かいとうといわねばなりません。
このお話は、そういう 出没自在しゅつぼつじざい、神変しんぺんふかしぎの怪賊と、日本一の名探偵めいたんてい明智小五郎あけちこごろうとの、力と力、知恵と知恵、火花をちらす、一騎きうちの大闘争だいとうそうの物語です。
大探偵明智小五郎には、 小林芳雄こばやしよしおという少年助手があります。このかわいらしい小探偵の、リスのようにびんしょうな活動も、なかなかの見ものでありましょう。
さて、前おきはこのくらいにして、いよいよ物語にうつることにします。
鉄のわな麻布あざぶ
の、とあるやしき町に、百メートル四方もあるような大邸宅があります。
四メートルぐらいもありそうな、高い高いコンクリート 塀べいが、ズーッと、目もはるかにつづいています。いかめしい鉄のとびらの門をはいると、大きなソテツが、ドッカリと植うわっていて、そのしげった葉の向こうに、りっぱな玄関が見えています。
いく 間まともしれぬ、広い日本建てと、黄色い化粧れんがをはりつめた、二階建ての大きな洋館とが、かぎの手にならんでいて、その裏には、公園のように、広くて美しいお庭があるのです。
これは、実業界の 大立者おおだてもの、羽柴壮太郎はしばそうたろう氏の邸宅です。
羽柴家には、今、ひじょうな喜びと、ひじょうな恐怖とが、織りまざるようにして、おそいかかっていました。
喜びというのは、今から十年以前に家出をした、長男の 壮一そういち君が、南洋ボルネオ島から、おとうさんにおわびをするために、日本へ帰ってくることでした。
壮一君は 生来せいらいの冒険児で、中学校を卒業すると、学友とふたりで、南洋の新天地に渡航し、何か壮快な事業をおこしたいと願ったのですが、父の壮太郎氏は、がんとしてそれをゆるさなかったので、とうとう、むだんで家をとびだし、小さな帆船はんせんに便乗して、南洋にわたったのでした。
それから十年間、壮一君からはまったくなんのたよりもなく、ゆくえさえわからなかったのですが、つい三ヵ月ほどまえ、とつぜん、ボルネオ島のサンダカンから手紙をよこして、やっと一人まえの男になったから、おとうさまにおわびに帰りたい、といってきたのです。
壮一君は現在では、サンダカン付近に大きなゴム植林をいとなんでいて、手紙には、そのゴム林の写真と、壮一君の最近の写真とが、同封してありました。もう三十歳です。 鼻下びかにきどったひげをはやして、りっぱな大人になっていました。
おとうさまも、おかあさまも、妹の 早苗さなえさんも、まだ小学生の弟の壮二そうじ君も、大喜びでした。下関しものせきで船をおりて、飛行機で帰ってくるというので、その日が待ちどおしくてしかたがありません。
さて、いっぽう羽柴家をおそった、ひじょうな恐怖といいますのは、ほかならぬ「二十面相」のおそろしい予告状です。予告状の文面は、
「余がいかなる人物であるかは、貴下きか
も新聞紙上にてご承知であろう。
貴下は、かつてロマノフ 王家おうけの宝冠ほうかんをかざりし大だいダイヤモンド六個を、貴家の家宝として、珍蔵ちんぞうせられると確聞かくぶんする。
余はこのたび、右六個のダイヤモンドを、貴下より無償にてゆずりうける決心をした。近日中にちょうだいに参上するつもりである。
正確な日時はおってご通知する。
ずいぶんご用心なさるがよかろう。」
というので、おわりに「二十面相」と署名してありました。
そのダイヤモンドというのは、ロシアの 帝政没落ていせいぼつらくののち、ある白系はっけいロシア人が、旧ロマノフ家の宝冠を手に入れて、かざりの宝石だけをとりはずし、それを、中国商人に売りわたしたのが、まわりまわって、日本の羽柴氏に買いとられたもので、価あたいにして二百万円という、貴重な宝物ほうもつでした。
その六個の宝石は、げんに、壮太郎氏の書斎の金庫の中におさまっているのですが、怪盗はそのありかまで、ちゃんと知りぬいているような文面です。
その予告状をうけとると、主人の壮太郎氏は、さすがに顔色もかえませんでしたが、夫人をはじめ、お嬢さんも、召使いなどまでが、ふるえあがってしまいました。
ことに羽柴家の支配人 近藤こんどう老人は、主家の一大事とばかりに、さわぎたてて、警察へ出頭しゅっとうして、保護をねがうやら、あたらしく、猛犬を買いいれるやら、あらゆる手段をめぐらして、賊の襲来しゅうらいにそなえました。
羽柴家の近所は、おまわりさんの一家が住んでおりましたが、近藤支配人は、そのおまわりさんにたのんで、非番の友だちを交代に呼んでもらい、いつも邸内には、二―三人のおまわりさんが、がんばっていてくれるようにはからいました。
そのうえ壮太郎氏の秘書が三人おります。おまわりさんと、秘書と、猛犬と、このげんじゅうな防備の中へ、いくら「二十面相」の怪賊にもせよ、しのびこむなんて、思いもよらぬことでしょう。
それにしても、待たれるのは、長男壮一君の帰宅でした。 徒手空拳としゅくうけん、南洋の島へおしわたって、今日こんにちの成功をおさめたほどの快男児ですから、この人さえ帰ってくれたら、家内のものは、どんなに心じょうぶだかしれません。
さて、その壮一君が、 羽田はねだ空港へつくという日の早朝のことです。
あかあかと秋の朝日がさしている、羽柴家の 土蔵どぞうの中から、ひとりの少年が、姿をあらわしました。小学生の壮二君です。
まだ朝食の用意もできない早朝ですから、邸内はひっそりと静まりかえっていました。早起きのスズメだけが、いせいよく、庭木の枝や、土蔵の屋根でさえずっています。
その早朝、壮二君がタオルのねまき姿で、しかも両手には、何かおそろしげな、鉄製の器械のようなものをだいて、土蔵の石段を庭へおりてきたのです。いったい、どうしたというのでしょう。おどろいたのはスズメばかりではありません。
壮二君はゆうべ、おそろしい夢をみました。「二十面相」の賊が、どこからか洋館の二階の書斎へしのびいり、宝物をうばいさった夢です。
賊は、おとうさまの居間にかけてあるお能の面のように、ぶきみに青ざめた、無表情な顔をしていました。そいつが、宝物をぬすむと、いきなり二階の窓をひらいて、まっくらな庭へとびおりたのです。
「ワッ。」といって目がさめると、それはさいわいにも夢でした。しかし、なんだか夢と同じことがおこりそうな気がしてしかたがありません。
「二十面相のやつは、きっと、あの窓から、とびおりるにちがいない。そして、庭をよこぎって逃げるにちがいない。」
壮二君は、そんなふうに信じこんでしまいました。
「あの窓の下には花壇がある。花壇がふみあらされるだろうなあ。」
そこまで空想したとき、壮二君の頭に、ヒョイと奇妙な考えがうかびました。
「ウン、そうだ。こいつは名案だ。あの花壇の中へわなをしかけておいてやろう。もし、ぼくの思っているとおりのことがおこるとしたら、賊は、あの花壇をよこぎるにちがいない。そこに、わなをしかけておけば、賊のやつ、うまくかかるかもしれないぞ。」
壮二君が思いついたわなというのは、去年でしたか、おとうさまのお友だちで、山林を経営している人が、鉄のわなを作らせたいといって、アメリカ製の見本を持ってきたことがあって、それがそのまま土蔵にしまってあるのを、よくおぼえていたからです。
壮二君は、その思いつきにむちゅうになってしまいました。広い庭の中に、一つぐらいわなをしかけておいたところで、はたして賊がそれにかかるかどうか、うたがわしい話ですが、そんなことを考えるよゆうはありません。ただもう、 無性むしょうにわなをしかけてみたくなったのです。そこで、いつにない早起きをして、ソッと土蔵にしのびこんで、大きな鉄の道具を、エッチラオッチラ持ちだしたというわけなのです。
壮二君は、いつか一度経験した、ネズミとりをかけたときの、なんだかワクワクするような、ゆかいな気持を思いだしました。しかし、こんどは、相手がネズミではなくて人間なのです。しかも「二十面相」という 希代きだいの怪賊なのです。ワクワクする気持は、ネズミのばあいの、十倍も二十倍も大きいものでした。
鉄わなを花壇のまんなかまで運ぶと、大きなのこぎりめのついた二つのわくを、力いっぱいグッとひらいて、うまくすえつけたうえ、わなと見えないように、そのへんの枯れ草を集めて、おおいかくしました。
もし賊がこの中へ足をふみいれたら、ネズミとりと同じぐあいに、たちまちパチンと両方ののこぎりめがあわさって、まるでまっ黒な、でっかい猛獣の歯のように、賊の足くびに、くいいってしまうのです。家の人がわなにかかってはたいへんですが、花壇のまんなかですから、賊でもなければ、めったにそんなところへふみこむ者はありません。
「これでよしと。でも、うまくいくかしら。まんいち、賊がこいつに足くびをはさまれて、動けなくなったら、さぞゆかいだろうなあ。どうかうまくいってくれますように。」
壮二君は、神さまにおいのりするようなかっこうをして、それから、ニヤニヤ笑いながら、家の中へはいっていきました。じつに子どもらしい思いつきでした。しかし少年の直感というものは、けっしてばかにできません。壮二君のしかけたわなが、のちにいたって、どんな重大な役目をはたすことになるか、読者諸君は、このわなのことを、よく 記憶きおくしておいていただきたいのです。
人か魔かその午後には、羽柴一家総動員をして、帰朝きちょう
の壮一君を、羽田空港に出むかえました。
飛行機からおりたった壮一君は、予期にたがわず、じつにさっそうたる姿でした。こげ茶色の薄がいとうを小わきにして、同じ色のダブル・ボタンの背広を、キチンと着こなし、折り目のただしいズボンが、スーッと長く見えて、映画の中の西洋人みたいな感じがしました。
同じこげ茶色のソフト 帽ぼうの下に、帽子の色とあまりちがわない、日にやけた赤銅色しゃくどういろの、でも美しい顔が、にこにこ笑っていました。濃い一文字もんじのまゆ、よく光る大きな目、笑うたびに見える、よくそろったまっ白な歯、それから、上くちびるの細くかりこんだ口ひげが、なんともいえぬなつかしさでした。写真とそっくりです。いや、写真よりいちだんとりっぱでした。
みんなと握手をかわすと、壮一君は、おとうさま、おかあさまにはさまれて、自動車にのりました。壮二君は、おねえさまや近藤老人といっしょに、あとの自動車でしたが、車が走るあいだも、うしろの窓からすいて見えるおにいさまの姿を、ジッと見つめていますと、なんだか、うれしさがこみあげてくるようでした。
帰宅して、一同が、壮一君をとりかこんで、何かと話しているうちに、もう夕方でした。食堂には、おかあさまの心づくしの晩さんが用意されました。
新しいテーブル・クロスでおおった、大きな食卓の上には、美しい秋の盛り花がかざられ、めいめいの席には、銀のナイフやフォークが、キラキラと光っていました。きょうは、いつもとちがって、チャンと正式に折りたたんだナプキンが出ていました。
食事中は、むろん壮一君が談話の中心でした。めずらしい南洋の話がつぎからつぎと語られました。そのあいだには、家出以前の、少年時代の思い出話も、さかんにとびだしました。
「壮二君、きみはその時分、まだあんよができるようになったばかりでね、ぼくの勉強部屋へ侵入して、机の上をひっかきまわしたりしたものだよ。いつかはインキつぼをひっくりかえして、その手で顔をなすったもんだから、黒んぼうみたいになってね、大さわぎをしたことがあるよ。ねえ、おかあさま。」
おかあさまは、そんなことがあったかしらと、よく思いだせませんでしたけれど、ただうれしさに、目に涙をうかべて、にこにことうなずいていらっしゃいました。
ところがです、読者諸君、こうした一家の喜びは、あるおそろしいできごとのために、じつにとつぜん、まるでバイオリンの糸が切れでもしたように、プッツリとたちきられてしまいました。
なんという心なしの悪魔でしょう。親子兄弟十年ぶりの再会、一生に一度というめでたい席上へ、そのしあわせをのろうかのように、あいつのぶきみな姿が、もうろうと立ちあらわれたのでありました。
思い出話のさいちゅうへ、秘書が一通の電報を持ってはいってきました。いくら話にむちゅうになっていても、電報とあっては、ひらいて見ないわけにはいきません。
壮太郎氏は、少し顔をしかめて、その電報を読みましたが、すると、どうしたことか、にわかにムッツリとだまりこんでしまったのです。
「おとうさま、何かご心配なことでも。」
壮一君が、目ばやくそれを見つけてたずねました。
「ウン、こまったものがとびこんできた。おまえたちに心配させたくないが、こういうものが来るようでは、今夜は、よほど用心しないといけない。」
そういって、お見せになった電報には、
「コンヤショウ一二ジ オヤクソクノモノウケトリニイク 二〇」
とありました。二〇というのは、「二十面相」の略語にちがいありません。「ショウ一二ジ」は、 正しょう十二時で、午前零時れいじかっきりに、ぬすみだすぞという、確信にみちた文意です。
「この二〇というのは、もしや、二十面相の賊のことではありませんか。」
壮一君がハッとしたように、おとうさまを見つめていいました。
「そうだよ。おまえよく知っているね。」
「下関上陸以来、たびたびそのうわさを聞きました。飛行機の中で新聞も読みました。とうとう、うちをねらったのですね。しかし、あいつは何をほしがっているのです。」
「わしは、おまえがいなくなってから、旧ロシア皇帝の宝冠をかざっていたダイヤモンドを、手に入れたのだよ。賊はそれをぬすんでみせるというのだ。」
そうして、壮太郎氏は、「二十面相」の賊について、またその予告状について、くわしく話して聞かせました。
「しかし、今夜はおまえがいてくれるので、心じょうぶだ。ひとつ、おまえとふたりで、宝石の前で、寝ずの番でもするかな。」
「ええ、それがよろしいでしょう。ぼくは腕力にかけては自信があります。帰宅そうそうお役にたてばうれしいと思います。」
たちまち、邸内にげんじゅうな警戒がしかれました。青くなった近藤支配人のさしずで、午後八時というのに、もう表門をはじめ、あらゆる出入り口がピッタリとしめられ、内がわから 錠じょうがおろされました。
「今夜だけは、どんなお客さまでも、おことわりするのだぞ。」
老人が召使いたちに 厳命げんめいしました。
夜を 徹てっして、三人の非番警官と、三人の秘書と、自動車運転手とが、手わけをして、各出入り口をかため、あるいは邸内を巡視する手はずでした。
羽柴夫人と早苗さんと壮二君とは、早くから寝室にひきこもるようにいいつけられました。
大ぜいの使用人たちは、一つの部屋にあつまって、おびえたようにボソボソとささやきあっています。
壮太郎氏と壮一君は、洋館の二階の書斎に 籠城ろうじょうすることになりました。書斎のテーブルには、サンドイッチとぶどう酒を用意させて、徹夜てつやのかくごです。
書斎のドアや窓にはみな、外がわからあかぬように、かぎや掛け金がかけられました。ほんとうにアリのはいいるすきまもないわけです。
さて、書斎に腰をおろすと、壮太郎氏が苦笑しながらいいました。
「少し用心が大げさすぎたかもしれないね。」
「いや、あいつにかかっては、どんな用心だって、大げさすぎることはありますまい。ぼくはさっきから、新聞のとじこみで、『二十面相』の事件を、すっかり研究してみましたが、読めば読むほど、おそろしいやつです。」
壮一君は真剣な顔で、さも不安らしく答えました。
「では、おまえは、これほどげんじゅうな防備をしても、まだ、賊がやってくるかもしれないというのかね。」
「ええ、おくびょうのようですけれど、なんだかそんな気がするのです。」
「だが、いったいどこから? ……賊が宝石を手に入れるためには、まず、高い塀を乗りこえなければならない。それから、大ぜいの人の目をかすめて、たとえここまで来たとしても、ドアを打ちやぶらなくてはならない。そして、わたしたちふたりとたたかわなければならない。しかも、それでおしまいじゃないのだ。宝石は、ダイヤルの文字のくみあわせを知らなくては、ひらくことのできない金庫の中にはいっているのだよ。いくら二十面相が魔法使いだって、この四重五重の 関門かんもんを、どうしてくぐりぬけられるものか。ハハハ……。」
壮太郎氏は大きな声で笑うのでした。でも、その笑い声には、何かしら 空虚くうきょな、からいばりみたいなひびきがまじっていました。
「しかし、おとうさん、新聞記事で見ますと、あいつはいく度も、まったく不可能としか考えられないようなことを、やすやすとなしとげているじゃありませんか。金庫に入れてあるから、大じょうぶだと安心していると、その金庫の背中に、ポッカリと大穴があいて、中の品物は、何もかもなくなっているという実例もあります。それからまた、五人のくっきょうな男が、見はりをしていても、いつのまにか、ねむり薬を飲まされて、かんじんのときには、みんなグッスリ寝こんでいたという例もあります。
あいつは、その時とばあいによって、どんな手段でも考えだす知恵を持っているのです。」
「おいおい壮一、おまえ、なんだか、賊を 賛美さんびしてるような口調だね。」
壮太郎氏は、あきれたように、わが子の顔をながめました。
「いいえ、賛美じゃありません。でも、あいつは研究すればするほど、おそろしいやつです。あいつの武器は腕力ではありません。知恵です。知恵の使い方によっては、ほとんど、この世にできないことはないですからね。」
父と子が、そんな議論をしているあいだに、夜はじょじょにふけていき、少し風がたってきたとみえて、サーッと吹きすぎる黒い風に、窓のガラスがコトコトと音をたてました。
「いや、おまえがあんまり賊を買いかぶっているもんだから、どうやらわしも、少し心配になってきたぞ。ひとつ宝石をたしかめておこう。金庫の裏に穴でもあいていては、たいへんだからね。」
壮太郎氏は笑いながら立ちあがって、部屋のすみの小型金庫に近づき、ダイヤルをまわし、とびらをひらいて、小さな赤銅製の小箱をとりだしました。そして、さもだいじそうに小箱をかかえて、もとのイスにもどると、それを壮一君とのあいだの丸テーブルの上におきました。
「ぼくは、はじめて拝見するわけですね。」
壮一君が、問題の宝石に好奇心を感じたらしく、目を光らせて言います。
「ウン、おまえには、はじめてだったね。さあ、これが、かつてロシア皇帝の頭にかがやいたことのあるダイヤだよ。」
小箱のふたがひらかれますと、目もくらむような虹の色がひらめきました。 大豆だいずほどもある、じつにみごとなダイヤモンドが六個、黒ビロードの台座の上に、かがやいていたのです。
壮一君が、じゅうぶん観賞するのを待って、小箱のふたがとじられました。
「この箱は、ここへおくことにしよう。金庫なんかよりは、おまえとわしと、四つの目でにらんでいるほうが、たしかだからね。」
「ええ、そのほうがいいでしょう。」
ふたりはもう、話すこともなくなって、小箱をのせたテーブルを中に、じっと、顔を見あわせていました。
ときどき、思いだしたように、風が窓のガラス戸を、コトコトいわせて吹きすぎます。どこか遠くのほうから、はげしく鳴きたてる犬の声が聞こえてきます。
「何時だね。」
「十一時四十三分です。あと、十七分……。」
壮一君が腕時計を見て答えると、それっきり、ふたりはまた、だまりこんでしまいました。見ると、さすが 豪胆ごうたんな壮太郎氏の顔も、いくらか青ざめて、ひたいにはうっすら汗がにじみだしています。壮一君も、ひざの上に、にぎりこぶしをかためて、歯をくいしばるようにしています。
ふたりの 息いきづかいや、腕時計の秒をきざむ音までが聞こえるほど、部屋のなかはしずまりかえっていました。
「もう何分だね。」
「あと十分です。」
するとそのとき、何か小さな白いものが、じゅうたんの上をコトコト走っていくのが、ふたりの目のすみにうつりました。おやっ、はつかネズミかしら。
壮太郎氏は思わずギョッとして、うしろの机の下をのぞきました。白いものは、どうやら机の下へかくれたらしく見えたからです。
「なあんだ、ピンポンの玉じゃないか。だが、こんなものが、どうしてころがってきたんだろう。」
机の下からそれを拾いとって、ふしぎそうにながめました。
「おかしいですね。壮二君が、そのへんの棚の上におきわすれておいたのが、何かのはずみで落ちたのじゃありませんか。」
「そうかもしれない……。だが時間は?」
壮太郎氏の時間をたずねる回数が、だんだんひんぱんになってくるのです。
「あと四分です。」
ふたりは目と目を見あわせました。秒をきざむ音がこわいようでした。
三分、二分、一分、ジリジリと、その時がせまってきます。二十面相はもう塀を乗りこえたかもしれません。今ごろは廊下を歩いているかもしれません……。いや、もうドアの外に来て、じっと耳をすましているかもしれません。
ああ、今にも、今にも、おそろしい音をたてて、ドアが 破壊はかいされるのではないでしょうか。
「おとうさん、どうかなすったのですか。」
「いや、いや、なんでもない。わしは二十面相なんかに負けやしない。」
そうはいうものの、壮太郎氏は、もうまっさおになって、両手でひたいをおさえているのです。
三十秒、二十秒、十秒と、ふたりの心臓の 鼓動こどうをあわせて、息づまるようなおそろしい秒時びょうじが、すぎさっていきました。
「おい、時間は?」
壮太郎氏の、うめくような声がたずねます。
「十二時一分すぎです。」
「なに、一分すぎた? ……アハハハ……、どうだ壮一、二十面相の予告状も、あてにならんじゃないか。宝石はここにちゃんとあるぞ。なんの異状もないぞ。」
壮太郎氏は、勝ちほこった気持で、大声に笑いました。しかし壮一君はニッコリともしません。
「ぼくは信じられません。宝石には、はたして異状がないでしょうか。二十面相は 違約いやくなんかする男でしょうか。」
「なにをいっているんだ。宝石は目の前にあるじゃないか。」
「でも、それは箱です。」
「すると、おまえは、箱だけがあって、中身のダイヤモンドがどうかしたとでもいうのか。」
「たしかめてみたいのです。たしかめるまでは安心できません。」
壮太郎氏は思わずたちあがって、赤銅の小箱を、両手でおさえつけました。壮一君も立ちあがりました。ふたりの目が、ほとんど一分のあいだ、何か異様ににらみあったまま動きませんでした。
「じゃ、あけてみよう。そんなばかなことがあるはずはない。」
パチンと小箱のふたがひらかれたのです。
と、同時に壮太郎氏の口から、
「アッ。」というさけび声が、ほとばしりました。
ないのです。黒ビロードの台座の上は、まったくからっぽなのです。 由緒ゆいしょ深い二百万円のダイヤモンドは、まるで蒸発でもしたように消えうせていたのでした。